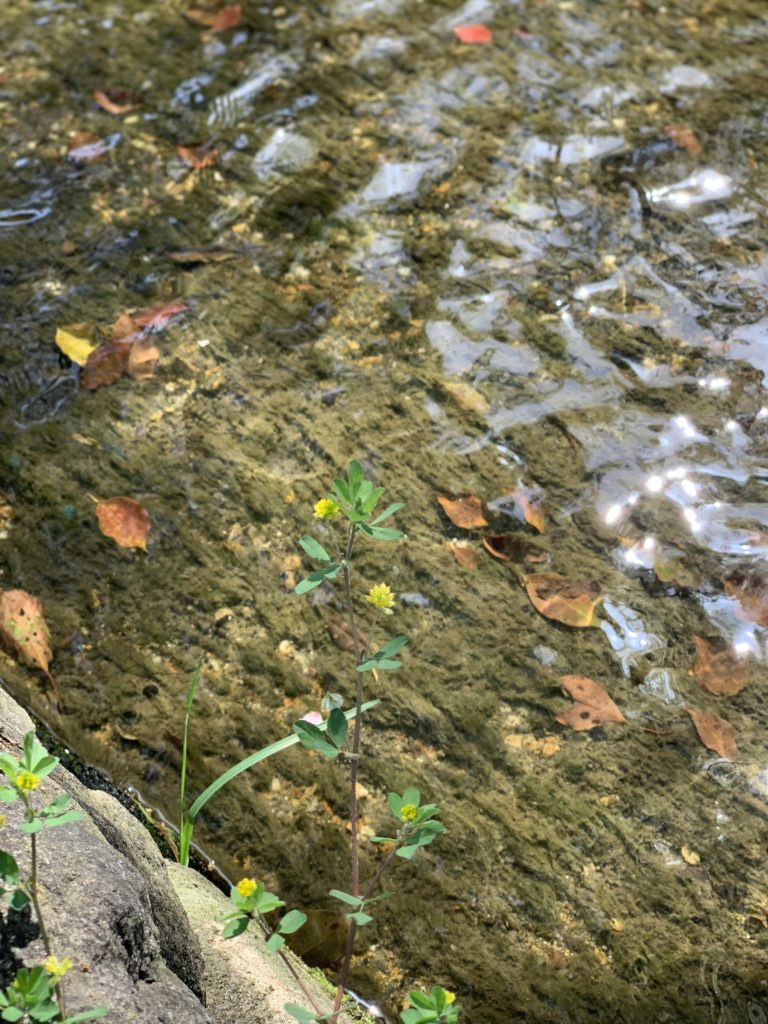今日はじゅらく児童館の「ピアノに合わせてあそぼう」の日でした。
今回の自己紹介のテーマは「好きな絵本」。月齢に合わせて選ぶ本も変わってきますよね。私も最近読み聞かせしているしこれからさらに増えると思うので(まご!)、どんな本が好まれているのか興味深いです。
今日の曲目
・おはようのうた
・こいのぼり
・めだかの学校
・ことりのうた
(手あそび)
・大きなたいこ
・おべんとうばこのうた
・あたまかたひざぽん
・おつかりありさん
・さんぽ
・おもちゃのチャチャチャ
(演奏)
・クレメンティソナチネ Op.36, No.4 第2楽章
・シューマン 五月、愛する五月
毎月季節の歌を入れながら色々な曲をやっていますが、とても有名なのにまだやっていない曲が何曲かあります。今後また取り入れてみたいです。