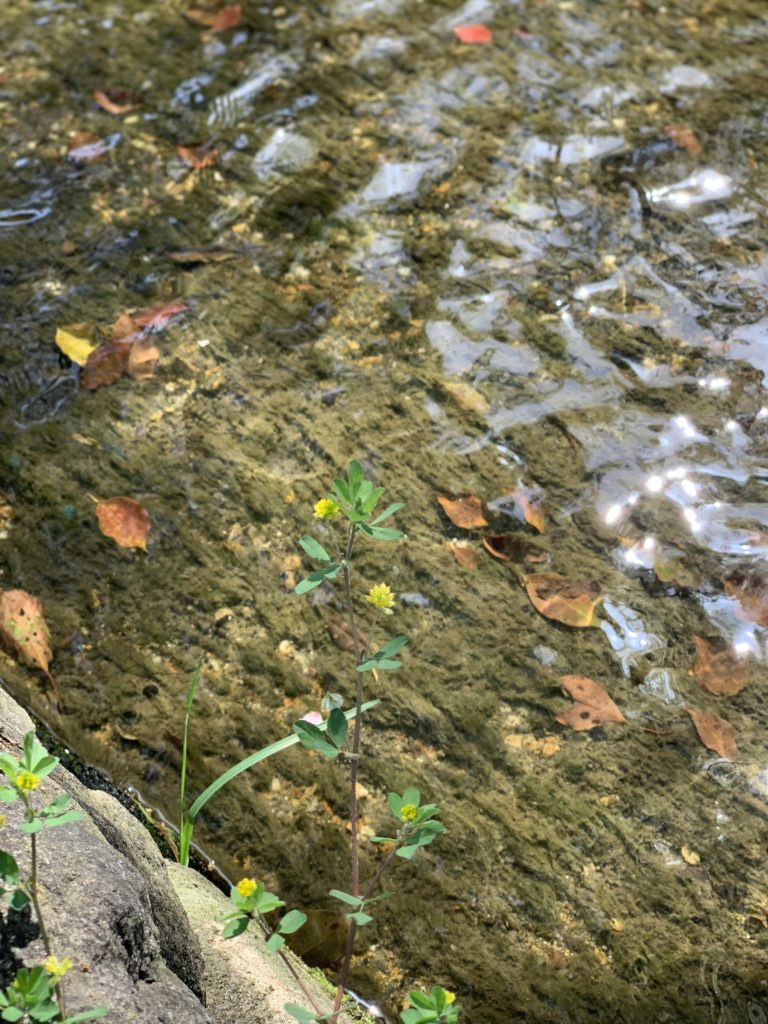10月21日、22日は保育士試験でした。2日連続の試験は思っていた以上にハードでした。
今年5月頃から保育士試験のテキストを買って勉強を始めました。試験科目は9科目。
「保育の心理学」「保育原理」「子ども家庭福祉」「社会福祉」「教育原理」「社会的養護」「子どもの保健」「子どもの食と栄養」「保育実習理論」です。多岐にわたりますが被っている部分もあります。
勉強を始めてすぐに、試験の内容は子どものことだけじゃなく、高齢者や障害者についてや貧困問題など、福祉全般に渡っていることがわかりました。保育士資格を持っている人は、保育所以外のいくつもの福祉施設で求められていることも知り、そのためにも多くの知識が求められるのだと思いました。
今後も子どもたちのいる場所で活動をしたり、もっと子育て支援のようなことにも関わりたい。仕事にしろボランティアにしろ、資格を持っていると何かとよいのではと思ったのが保育士試験を受けようと思った理由のひとつです。
私が保育士試験を受けると知ったケアマネージャーの友だちは、何種類かの高齢者施設のちらしをラインで送ってきました。どこでもいけるよーと。へーやっぱりそうなんとちょっと驚きました。でも、とりあえず、資格とっても保育士として働くわけではないし、高齢者の所も念頭にはないよと返事しました(音楽活動は機会があればやらせていただきたいです)。
試験の勉強なので、広く浅くになってしまうけど、中に気になるテーマがいくつもあり、試験ではそこまで必要ないけど調べて見たり、試験終わったら改めて調べてみようと思ったことがいくつかあります。
「保育の心理学」は昨年度履修した発達心理学(京都橘大学)とも内容が被っている部分がいくつもあり、改めてやはり興味深い分野だと思いました。
テキスト2冊(たくさんある中から適当に選んだ上下巻)を一通り読み、過去問題集も一冊やり(アプリやサイトも利用)、様々な保育士試験関連YouTube動画を聞き、疑問に思ったことは検索しまくり、再びテキストを読みました。それでも、試験範囲はあってないようなもので、様々な法律や制度や統計など何が出るかわからない。実際、今回の試験でも見たことも聞いたこともないことがいくつか出ていました。
まあ、テキストに書いてあったことだけでも、盛りだくさんでとても覚えきれていませんが。
23日、解答速報が出るようなので、ドキドキしながら答え合わせしようと思います(笑)。