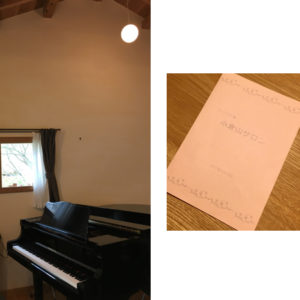前回、少しリトミックについて書きましたが、その後、読みかけで置いていた『音楽表現』(福村出版)という保育者向けに書かれた本を開いてみました。ちょうどしおりを挟んでいた所がエミール・ジャック=ダルクローズのリトミックについて書かれている箇所でした。
また、本棚にもリトミックに関する本が何冊かあるので、久しぶりに開いてみました(関心が薄れていましたが、一時はわりと調べていました)。
前回は、記憶している範囲を元に書きましたが、まずダルクローズのリトミックについて簡単に書いてみたいと思います。本によって少し表現が違いますが、まず『音楽表現』の内容を参考にします。
ダルクローズのリトミックの3要素は、リズム運動、ソルフェージュ、即興演奏です。
・リズム運動は身体運動を通して行います。
身体運動には次の3原則があります。
①時間:長い(遅い)・中・短い(早い)
②空間:広い・中・狭い
③エネルギー:大きい・中・小さい
・ソルフェージュは歌うことにより、音の高さ、音の関係、音の質について聴き分ける力を養います。
・即興演奏はリズム、ソルフェージュを融合させたピアノによるその場での作曲です。
これらの内容は、私が参加していたダルクローズのリトミック研究会でのレッスンの内容と同じだと思います。
で、子どもに向けたリトミックはこれらを元に、子どもができる内容に変えることになりますね。
それについては、『1~5歳のかんたんリトミック』(ナツメ社)の中に書かれています。
・リズム運動:歩く、走る、跳ぶなどの動きの中から音楽的な感覚を味わう。
・ソルフェージュ:リズム運動の体験を音と関連付ける。旋律に合わせ体を動かすなど。
・即興演奏:リズム運動、ソルフェージュの体験をもとに自分なりの表現をする。
こちらの本の具体的な内容を見ていると、いつも児童館でやっているような歌と手遊びも出てきます。子ども向けの音楽遊びにはあまり意識はしていなくてもリトミック的な要素は含まれているわけですね。この本は何年も前に目を通しているので、当時も同じように思っていたかもしれません。
リトミックは一つのメソッドで、他にも子ども向けの音楽メソッドはあります。
コダーイのメソッドがあることは保育士試験の勉強で知りました。『音楽表現』はコダーイのメソッドについて知りたくて見つけた本です。
詳しく知りませんがオルフのメソッドもあります。
これらは手段で、結局子どもにとってどのような音楽遊びが楽しくて望ましいのかというのが大切で、よいと思えることは取り入れればいいのかなと思います。
児童館でお手伝いしているイベントでは2歳までの乳幼児が多く、できることも限られていますが、もしまた別の場所などで機会があればもう少し違った内容も取り入れられたらと考えています。